今週は高知学芸中学より1問です。

下の(あ)~ (え)は同じ立方体の展開図です。(い)(う)(え)の展開図に残りの数字を、向きに注意して書き入れ、展開図を完成させなさい。(高知学芸中)
(あ)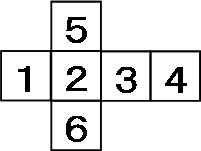
(い)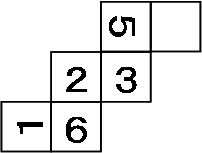
(う)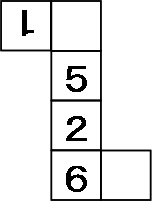
(え)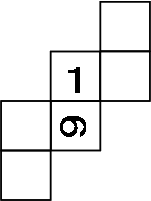

方向感覚が狂わないように、工夫してみましょう。

(い)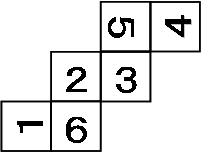
(う)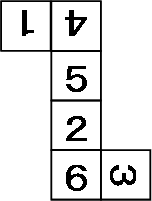
(え)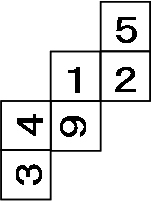

(あ) のように、上下左右をきちんと記入します。
(い)で考えるときには、○の部分は明らかに3の右と一致します。
(あ)では、3の右と接しているのは4の左なので、方向が確定します。
このように、立体図形や平面図形の移動、折りたたみの問題において、
方向を常に正しく把握するためには、丁寧な作業が重要です。
(あ)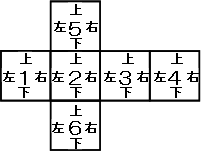
(い)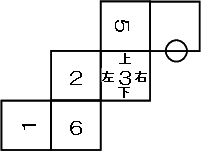
万が一にも間違えたくはない問題、しかも確認が難しいタイプの問題では、
このような面倒でも確実な工夫が、見直しを含めると一番の近道になるのです。
~今回の問題から導かれる出題校からのメッセージ~
・ 確実性を担保する視点を見つける能力が重要
「見直しをする力」これは、注意力などケアレスミスをなくすための能力にとどまらず、
「その観点から計算してみても成立していれば答えに誤りはない」
という自らの解法とは別の観点を見つける能力のことです。
確実なものは何か、不確実なものは何か。
そして、その不確実性はどの観点からの確認で払拭されるものなのか。
見直しは、自らの計算の足跡をなぞるものではありません。
考え得る様々な視点で検証する姿勢こそが、
未知の分野を切り開く人間に必要な能力なのです。
100%確実なものと、99%以下のものをきちんと見分ける。
100%確実なものを根拠とする姿勢を身につける。
「センス」「ひらめき」による筋道を、確実なものとする論理性。
レベルの高い学校ほど、「柔軟な発想による方針策定」と
「地道な検証」の両方を必要とする問題を出題してきます。