今週 は桜蔭中より1問です。

『カエルが、からだのどこを使って産卵池の位置を知るのか』を 調べるために以下の実験を行いました。
【実験】池に向かうカエルを池から50~200m離れたところでつかまえて,3つのグループ(う)、(え)、(お)に分け、以下のようにしました。
グループ(う):目が見えないようにした後、(う)の目印をつける
グループ(え):鼻でにおいがかげないようにした後、(え)の目印をつける
グループ(お):目や鼻には何もせず、(お)の目印をつける
グループ(う)、(え)、(お)のカエルをつかまえた場所で放し、1週間で、どれくらい池にたどり着いたかを調べた結果が図3です。
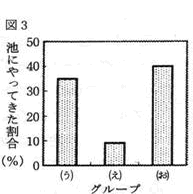
問4 【実験】の結果について、つぎの問い(1)~(4)に答えなさい。
(1) 池の位置を知るのに、カエルが主に目を使って いるといえる場合は○、いえない場合は×を書きなさい。
(2) (1)はグループ(う)~(お)のどれとどれ の結果を比べるとわかりますか。
(3) 池の位置を知るのに,カエルが主に鼻を使って いるといえる場合は○、いえない場合は×を書きなさい。
(4) (3)はグループ(う)~(お)のどれとどれ の結果を比べるとわかりますか。
(桜蔭中)

上記、(1)から(4)を解くにはヒントはい らないと思います。この問題は、解答の先にとても大事な考え方を知るチャンスがあります。必ず解説にも目を通してください。

(1) ×
(2) (う)と(お)
(3)○
(4) (え)と(お)

こ の問題の隠れたポイントは、
(2)で、なぜ、(う)と(え)をくらべてはいけないか
(3)で、なぜ、(う)と(え)をくらべてはいけないか
が説明できるかどうかです。
(上記が説明できなくても試験では解答できてしまうのが残念なところです)
グループ(う) → 目隠し
グループ(え) → 鼻せん
グループ(お) → なにもしない
ソラマメの発芽実験問題が有名ですが、この問題も対照実験について扱った問題です。
「対照実験とは」 → 「比べることにより結果の理由を特定する実験」
→ 「2者の異なる点が1つだけならば、生じた結果の原因は、その異なる点だと結論ずける方法論」
グループ(う)とグループ(お)
・・・・ 異なる点は、「目隠しをしているかどうか」 の1点
グループ(う)とグループ(え)
・・・・ 異なる点は、「目隠しをしているかどうか」と、「鼻せんをしているかどうか」の2点
となります。グループ(う)とグループ(え)を比べても、池に帰ってくるカエルの割合が違う原因が、特定できないのです。異なる点が2つあるからです。ど ちらが理由なのか特定できません。
この問題は、本来、
「カエルが目をあまり使っていない」ことを言うために、(う)と(え)をくらべてはいけない理由を説明しなさい。
とするべきだったのではないでしょうか。 (答えは、「(う)と(え)は異なる点が2つあるから」)
「一つの結論に対して、一つだけの相違点をみつける」
対照実験の根本を理解しているかを確認してください。
~今回の問題から導かれる出題校からのメッセージ~
「対照実験」のような基本的方法論の徹底理解をすること
以前にも同様のメッセージを読み解きました。とかく頻出の対照実験問題ですが、
上位校ほどその根本的意味の理解を確認してきます。
さて、教室で本問を扱いました。学年問わず8割の生徒は正解できましたが、こと、
(2)で、なぜ、(う)と(え)をくらべてはいけないか
(3)で、なぜ、(う)と(え)をくらべてはいけないか
という問いを追加すると、白紙になってしまう生徒がほとんどでした。
(対照実験の意味が理解できていない証拠です。)
「目隠ししても、多くのカエルが帰ってくるけど、
鼻せんをすると、ほとんどのカエルがかえってこられない。」
日常の感覚だと、上のセンテンスからでも、「カエルにとって目は大事ではない」と
結論づけることもできそうです。
しかし、この日常の感覚を疑い、科学的な方法論で物事を判断するスキルを
桜蔭中は求めているのです。
「感覚を疑え!」などと格好良く言い放つことは簡単ですが、「疑い方」が伝えられていないのが
現在の理科教育の現状ではないでしょうか。
「感覚を疑う」ことは、闇雲に疑心暗鬼になることではありません。
また、「感覚」は否定すべきものではありません。
自分の直感・常識・感覚を補強し、視点を増やすために、対照実験のような基本的な方法論を
徹底的に理解する必要があるのです。