頌栄女子学院中より。複数段階の論理展開を行うための基礎的な問題。

ニュージーランドの方が日本よりも年間の気温の変化が小さくなっています。これには、
冬にあたる時期の気温の違いが大きく関わってきます。同じ島国でありながら、
日本の冬の気温は低く、ニュージーランドの冬の気温は比較的暖かいのはなぜですか。次のヒントをもとに説明しなさい。
《ヒント1》
水は温まりにくく冷めにくい物質である。岩石や砂、土などには、水に比べると温まりやすく冷めやすい。
《ヒント2》
それぞれの国の周りの様子(下図)
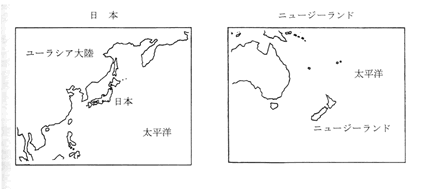
(頌栄女子学院中)


日本は、温度変化の大きい大陸が近くにあり、大陸が冷えた際の影響を受け気温が下がる。
これに対し、ニュージーランドは、まわりを広い海に囲まれており、冬になって冷やされても温度の変化が小さく、
海水が冷えることでの影響が少ない。
このため 同じ島国でありながら日本とニュージーランドでは冬の気温差が生じる。

ヒント1 ⇒ 水は温度変化が小さい ⇒ 海は冬になっても、陸ほど温度が下がらない。
⇒ 岩石・砂・土は温度変化が大きい ⇒ 陸は冬になると、海よりも温度が下がる。
~今回の問題より導かれる出題校からのメッセージ~
複数段階の「だから」をつかった論理展開ができるようになってほしい
「良問」と言われる問題の多くによく見られるパターンですが、
単に、
条件・ヒント ⇒ 結論・解答
というプロセスを求めるのではなく、
条件・ヒント ⇒(だから)⇒ 考察 ⇒(だから)⇒ 考察 ⇒(だから)⇒ 結論・解答
というように、確実に「だから」でつながる事象をつなげたり、時には言えそうな予想(仮説)をたて、
複数段階にわたって「だから」思考の積み重ねを要します。
本問は、ヒント⇒考察⇒解答 という比較的平易な種類の論理展開での解答が可能ですが、
同様の問題でも考察が数段階になったとたん多くの受験生にとって「難問」となってしまうのが、
教室での実感です。
1つの知識を学んだら、そこから「だから」を使って派生させ周辺知識を覚えるという習慣を身につけましょう。
多くの成人に関しても「だから」が正しく使われているかはそもそも疑問です。
小学生のうちから「だから」で思考を広げる訓練を積みたいものです。