大問における小設問は、いわば「ヒント」に他なりません。

生物は呼吸をします。
呼吸とは、空気中の酸素と体の中の栄養分を結びつけて、生きるために必要なエネルギーを取り出すことです。
この反応で使われた栄養は二酸化炭素と水になって体の外に放出されます。
呼吸に必要な栄養分(呼吸材料)には、ブドウ糖、脂肪、タンパク質があります。
呼吸材料の種類によって、反応するのに必要な酸素の割合がちがうので、
生物がどの呼吸材料を使って呼吸をしているのかは、
放出された二酸化炭素と吸収した酸素の体積比で調べることができます。この比を呼吸商といい、
以下の計算式で求めることができます。
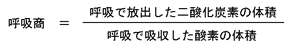
ブドウ糖、脂肪、タンパク質がそれぞれ呼吸材料として使われた場合の呼吸商の値を調べると、次のようになることが分かっています。
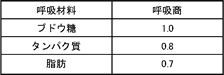
発芽直後のダイズ種子について呼吸の状態を調べるために、図のような装置を使って実験をしました。
[実験]
図のように、赤い水滴が同じ位置に入った装置A、Bを用意し、光を当てて3時間おき、ガラス管内の水滴の移動を調べました。なお、装置Bで用いる濃い水酸化ナトリウム水溶液は、空気中の二酸化炭素を吸収するはたらきがあります。
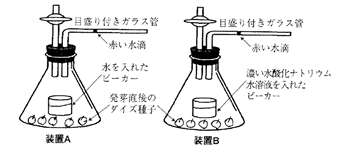
結果]
装置A:ガラス管内の水滴が、左の方向に4目盛り動いた。
装置B:ガラス管内の水滴が、左の方向に20目盛り動いた。
このとき、実験に用いた発芽直後のダイズ種子の呼吸商の値を求めなさい。
(栄東 東大選抜)

装置A、Bのガラス管内の水滴の移動は、どうして起こったのでしょうか。

0.8

まず、それぞれの装置で水滴が動いた理由を考えます。
A、Bどちらも水滴が左に動いていることから、フラスコ内の気体の量が減少していることは間違いありません。
発芽したばかりの種子は、激しく呼吸をすることから(これはこの問題の流れから容易に読み取れます)酸素が減少することはわかります。
ここで、装置A、Bのちがいは水酸化ナトリウム水溶液の有無です。
水酸化ナトリウム水溶液のあるBでは、もともとフラスコ内に二酸化炭素はなく、さらに呼吸によって発生した二酸化炭素も吸収されてしまうため、実験の前後では酸素の量しか変化はありません。
一方で、装置Aでは呼吸に使われた酸素が減る一方で、発生した二酸化炭素の分気体の量は増えます。つまり、この差の分だけフラスコの体積が減ることになるのです。
このことから考えれば、装置A、Bでの水滴の動いた目盛りの差は、発生した(呼吸によって放出した)二酸化炭素の量であることがわかります。
これより、以下のとおり呼吸商が求められます。
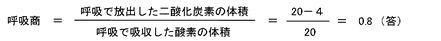
[以上、2008栄東・東大選抜より一部抜粋]
さて、この問題がヒントなしですんなりと解答できたでしょうか。
このやや長いリード文と初めて聞く「呼吸商」という言葉から考えるとこれは難問の部類に入るでしょう。
正しい理論を持って、正答を導くにはかなりの時間を要した受験生が多かったはずです。
何よりも、装置A、Bの違いが二酸化炭素に関係することはわかっても、答えをどのように導き出してよいかわからないためです。
しかし、実際の入試問題ではこの設問の前に次のような設問が用意されています。
問 装置A、Bのガラス管内の水滴の移動は、それぞれ何の体積が変化したことによるものですか。次のア~キから選び、記号で答えなさい。
ア 呼吸により生じた二酸化酸素の体積
イ 呼吸により吸収された酸素の体積
ウ 呼吸により生じた二酸化炭素の体積と吸収された酸素の体積の差
工 光合成により生じた酸素の体積
オ 光合成により吸収された二酸化炭素の体積
力 光合成により生じた酸素の体積と吸収された二酸化炭素の体積の差
キ 呼吸および光合成により出入りした酸素の体積と二酸化炭素の体積の差
まさに、今回「ヒント」として与えた内容です。
これにより、装置A、Bの差異が明確になり、正答までの距離が大きく短縮されます。
ただ「初見問題を解くときは知らないからという理由だけであきらめないという姿勢が大切」というだけでなく、
具体的に身近なところからヒントを探る意識を持ちましょう。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
~2箇所でブログランキングに参加しています~
1.
2.![]()
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ところで、こんなのはじめました。
参考書選びの参考にご利用ください。
ロジム2階参考書コーナー