複雑な回路を流れる電流

下の図のように、豆電球3つと乾電池2つとスイッチ3つを使って回路をつくりました。いま、A~Cのスイッチはどれも入っていませんが、アとウの豆電球が光っていました。これについて、次の問いに答えなさい。
(1) Aのスイッチだけを入れると、ア~ウのうちどの豆電球が光りますか。
(2) すべてのスイッチを入れると、ア~ウのうちどの豆電球が光りますか。
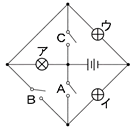

電流の気持ちになってください。

(1) ア、イ、ウ
(2) イ、ウ

まず、電流が流れるルールを確認しましょう。
豆電球は電気抵抗なので、豆電球が多ければ多いほど電流は流れにくくなります。特に、豆電球を並列につないだ場合、それぞれを流れる電流の大きさは豆電球の個数の逆比になります。
たとえば、豆電球1個と2個を並列(道が分かれている状態)につないだ場合、流れる電流は2:1となるのです。
このことから、下の図のように、もしも分かれた道の一方に豆電球がなかった場合、豆電球のある方へ流れる電流が0となり、すべての電流が豆電球のない道を選んで流れることになります。
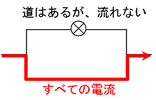
このように、複数のスイッチや並列部分をふくむ複雑な回路では、どこを電流が流れるのか(どこを電流が流れないのか)をきちんと調べることが重要です。この際にポイントとなるのが「道が分かれたら再び合流する位置を探し、それぞれの道で豆電球がない道があればそこしか電流は流れない」ということです。
(1) まず、説明のために、図1のように各地点を「あ」~「お」とします。
電池を出た電流は「あ」で道が分かれます。このとき、「い」へ向かう電流と「え」へ向かう電流が合流する地点は「お」しかありません。
このとき、どちらの道にも豆電球があるので、どちらも流れることになります(流れる電流の大きさの比は、1:2ですね)。
(2) 図1と同様に「あ」~「お」とします。電池を出た電流は「あ」で道が分かれます。
このとき、「い」と「う」と「え」に向かって電流が流れていきます。
ここで、次の3つの場合を考えてみましょう。
1.「い」で合流する場合・・・「あ-い」の間は流れません(この道だけ豆電球があるため)。
2.「う」で合流する場合・・・「あ-い」の間は流れません(この道だけ豆電球があるため)。
3.「え」で合流する場合・・・「あ-い」の間は流れません(この道だけ豆電球があるため)。
よって、どこで合流するにせよ、「あ-い」の間を通らなくてすむ道があるので、「い」に向かっては流れないことがわかります。
「う」と「え」に分かれて流れた電流は、このあと「お」で合流することになりますが、この場合どちらも豆電球があるのでどちらにも流れることになります。
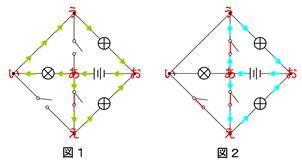
では、スイッチAとBのみを入れた場合はどうなるでしょう?
ぜひ、考えてみてください。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
~2箇所でブログランキングに参加しています~
1.
2.![]()
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ところで、こんなのはじめました。
参考書選びの参考にご利用ください。
ロジム2階参考書コーナー