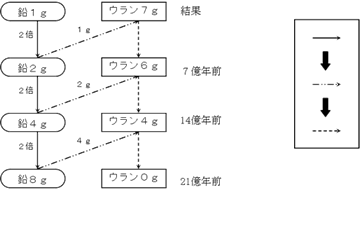前回に続き、新傾向問題は「誘導にのれるか」が勝負の鍵です。 2008-11-03
前回に続き、新傾向問題は「誘導にのれるか」が勝負の鍵です。

生物が子孫を残すとき、多くの場合で子は親と似ていることに気がついた太郎君は、図書館でいろいろと調べてみました。
すると、親の持っている特徴は子に伝わっていき、それを遺伝とよぶことを知りました。
また、この遺伝について最初に詳しい研究をしたのは、オーストリアの司祭であったメンデルです。
メンデルは、エンドウという植物を観察していたところ、図1のような2種類の形の種子があることに気づきました。
そして、その形のちがいを利用して、次のような4つの実験を行いました。これについて、あとの問いに答えなさい。
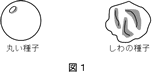
<実験1> 丸い種子をまいて受粉をくり返すと、何度受粉をしても丸い種子しかできなかった。
<実験2> しわの種子をまいて受粉をくり返すと、何度受粉をしてもしわの種子しかできなかった。
<実験3> 実験1、2でできた丸い種子としわの種子をまいて、人工的に一方の花粉をもう一方のめしべに付けると、その子は丸い種子しかできなかった。
<実験4> 実験3のあと、子の種子をまいて受粉させて孫を作ったところ、丸い種子としわの種子ができた。
種子を丸くする遺伝子をX、種子をしわにする遺伝子をYとすると、実験1で作った種子のもつ遺伝子はXXとなり、実験2で作った種子のもつ遺伝子はYYとなるはずです。実験3で、丸い種子の親から子へ伝わる遺伝子はX、しわの種子の親から伝わる遺伝子はYとなるので、表1のように子のもつ遺伝子はすべてXYとなることがわかります。
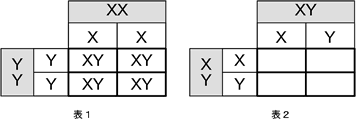
ここで、種子を丸くする遺伝子Xの方が、種子をしわにする遺伝子Yよりも強くあらわれる性質をもっているので、子はすべて丸い種子であることが説明できるのです。
そして、この性質を優性とよびます。実験4では、XYの遺伝子をもつ子が親になって孫をつくるので、表2のように孫のもつ遺伝子は4通り考えられます。ただし、表の中には実際の孫の遺伝子の組み合わせは書かれていません。
問1
実験4でつくった孫の種子について、丸い種子としわの種子の割合は何:何ですか。
問2
実験4でつくった孫の種子をすべてまき、自然に受粉をさせると、丸い種子としわの種子の割合は何:何になりますか。
ただし、エンドウは自然界では自家受粉を行います。
問3
オシロイバナは、不完全優性という性質をもつ植物です。
例えば、オシロイバナの赤い花と白い花で子を作ると、子はピンク色の花をさかせます。
これは、赤い花になる優性の遺伝子Pが不完全であるために、白い花になる遺伝子QとでできたPQが、赤ではなく中間のピンク色になってしまうのです。ピンク色の花と白い花で子を作ると、赤色の花は何%の割合であらわれますか。

ただ「決まり」に従うだけです。

問1 3:1
問2 5:3
問3 0%

問1 それぞれの遺伝子を組み合わせると、下の図 のようになります(赤=丸い種子)。
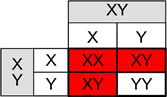
問2 自家受粉をするエンドウは、人工的に手を加 えない限りその花の中で受粉が行われるので、同じ 組み合わせの遺伝子で遺伝が繰り返されていきます。 よって、問1の4つの組み合わせに対して、下の図 のような組み合わせが考えられます。
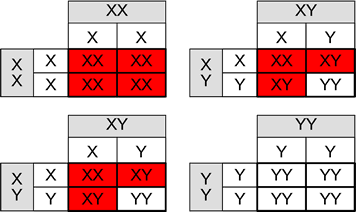
問3 ピンク色の花がもつ遺伝子の組み合わせはPQ、 白色の花がもつ遺伝子の組み合わせはQQなので、右 の図のような遺伝になります。ここで、赤色の花がも つ遺伝子はPPしかないので、この場合赤色の花がさ くことはないことがわかります。
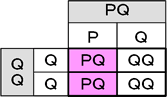
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
~2箇所でブログランキングに参加しています~
1.
2.![]()
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ところで、こんなのはじめました。
参考書選びの参考にご利用ください。
ロジム2階参考書コーナー
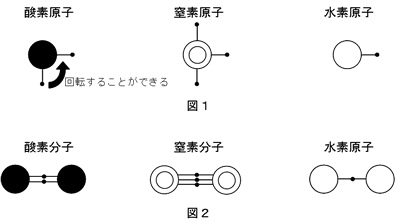
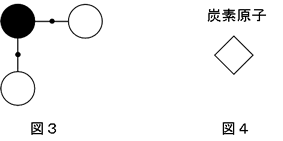
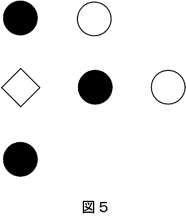
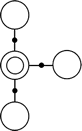
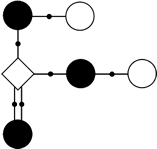
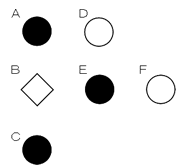
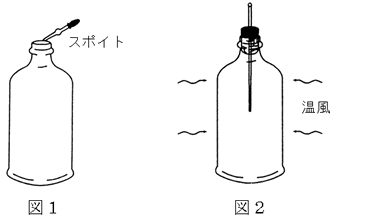
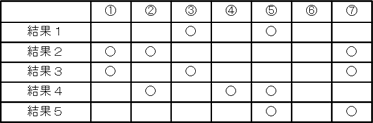
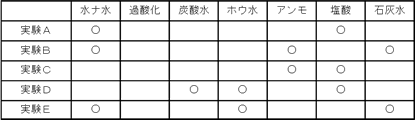
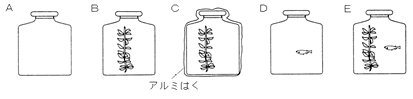
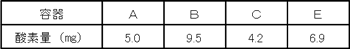
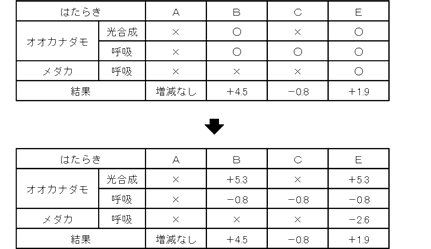
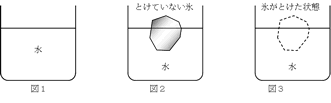
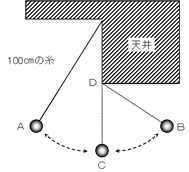

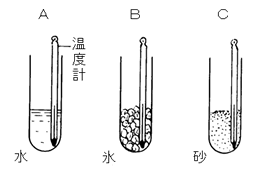
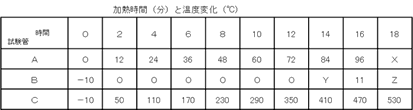
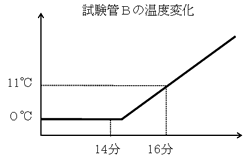
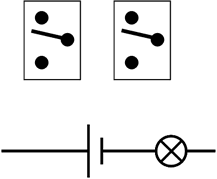
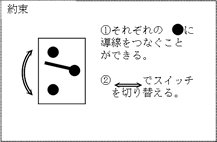
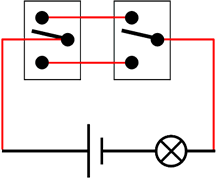
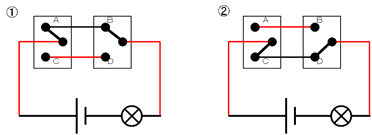
 まず1本の道を作ります(上の図A-B)。
まず1本の道を作ります(上の図A-B)。 切り替え用に別にもう1本の道を作ります(上の図のC-D)。
切り替え用に別にもう1本の道を作ります(上の図のC-D)。