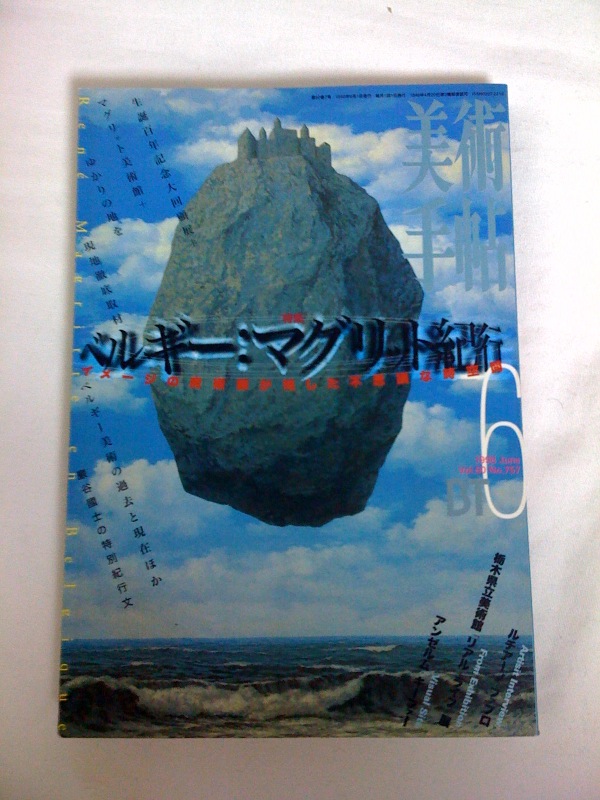国語が出来てしまう子
こんにちは竹村です。
教室で教えていると比較的よく目にするのですが、国語が出来てしまう子、というのが結構います。蓄積されているストーリーや例文の量が豊かで、いわゆる読解力が高く、「なんとなく勘で」解けてしまうタイプ。どうしてこうなるの?と聞くと「・・・だってそうだから?」
「それ以外おかしくない?」と言う返事が多いです。基礎の言語能力が充実しているので、安定していて有利なように思えますが、じつはこれはこれで厄介なタイプです。
大昔の話ですが、私自身小学生の頃はこんなタイプの生徒でした。
何が問題かというと、「何が間違っている(正しい)のか分からない」のに、点数は平均点を下回ったりすることがまずないために危機感を覚えない、というのが最大の問題です。
国語の読解というのは、本来とても点数のつけづらい分野です。しかし、多数の人間に優劣をつけるテストの問題では、なんとなく○なんとなく×と言うわけには行きません。入試ともなればなおさらです。公平性の確保のためにどうしても採点基準の明確化が求められます。
そのため、いくつかの基本的な解答の「型」が用意されることになります。問題を解く際は、その型にそって必要な部分を把握して過不足ないように解答する。その際、必要な部分が何であるかを判断するために、論理の流れにしがみついて追っていくことになります。最後に、言語感覚、いわゆる「勘」に照らし合わせて違和感がないかをチェックします。
授業では、語彙を豊かにしたり、感情や論理の流れ方のパターンを増やすトレーニングも行います。
しかし、読解問題を解かせる時に養うのはこの論理にしがみついていく力と方法、また(枝葉末節に
響くかもしれませんが)「型」にそった正確なアウトプットが中心となります。
上記のタイプの子どもは、このプロセスの把握が出来ておらずそういった能力がほとんど身についていないのにもかかわらず、そういった自覚がないことがとても多いです。
さらに、授業中それを説明しても問題の正解数が多いために満足してしまい説明に注意を払わないことも非常に多いです。せっかく授業に来ているのに、持って帰れるものが
半減してしまいます。
目立つ特徴として、点数が非常にばらつきます。極端な例だと、偏差値50強~70弱くらいの間を振り子のようにぶんぶんとスイングします。的を狙う方法を知らないのだから、刺さる先がばらばらなのは当然です。
なかなか周囲が気がつかないケースも多いので、是非注意してあげてみてください。